大川常吉之碑見学(鶴見東漸寺にて)-320x180.jpg) 活動記録
活動記録 2022年度 秋のフィールドワーク
2022年度 秋のフィールドワーク 目的 韓国併合から13年後の1923年、関東大震災が首都圏を襲います。震災の直後に広まった流言飛語を信じた人々は、朝鮮や中国から来た人々を無差別に殺戮しました。保護しようとした警察署も暴徒に襲われ、警官...
大川常吉之碑見学(鶴見東漸寺にて)-320x180.jpg) 活動記録
活動記録 2022年度夏合宿(仁徳天皇陵拝所)-320x180.jpeg) 活動記録
活動記録 編・画『前賢故実』巻之四より)-320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 -320x180.png) 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 -320x180.png) 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 -320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 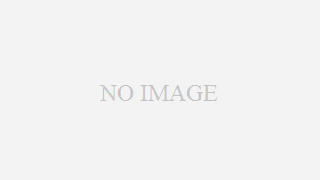 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 (東京国立博物館)-320x180.jpg) 日中交流の史跡と文化
日中交流の史跡と文化 -320x180.jpeg) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 ジオラマ(飛鳥資料館)-320x180.jpg) 2025年度授業計画
2025年度授業計画