1.アイス・ブレーキング
13:10~13:30 合宿での活動について
2.輪読発表とグループワーク
13:30~14:00 輪読発表
【課題図書】Ⅱ 倭の王権と朝鮮三国――虚像と実像
14:00〜14:20 グループワーク
- 永楽6年だけ、第一類型の例外となっている(年次と王王躬率の間に理由が書かれていない)理由は何か?(pp.56 3-8行目)
【課題図書】テーマ「課題図書を読んで興味を感じたところ、疑問に思ったところ」
14:20~14:30 休憩
3.新聞発表とグループワーク
14:30~14:50 新聞発表
【新聞記事】「北朝鮮、『イムジン河』視聴禁止」(朝日新聞2024年6月8日夕刊)
14:50~15:10 グループワーク
- テーマ「この北朝鮮でのイムジン河の視聴禁止は、今後の日本と北朝鮮の関係にどう影響するか?」
15:10〜15:15 休憩
4.補足説明
15:15~16:00
- 本居宣長以来、紀年に疑問が持たれてきた『日本書記』でしたが、那珂通世(1851-1908)の研究(1897年に『史学雑誌』に発表した「上世年紀考」など)により、神功皇后の時代の紀年が、実際の年よりも120年繰り上げられていることが明らかになりました。しかし、なぜ『日本書紀』の編者は、神功皇后の時代を120年繰り上げたのでしょうか。
干支二運繰り上げ説
七枝刀は、奈良県天理市の石上神宮に伝わってきました。‥‥表面をおおっていた錆をおとし、文字が刻まれていることを発見したのは、明治初期に石上神宮の宮司をつとめていた菅政友でした。銘文は、表面に34字、裏面に27字があり、金で象嵌されていました。
ところで、『日本書紀』によると‥‥(神功皇后の)52年に、百済王の使者久氐がきて、服属のしるしに「七枝刀」を献上したというのです。
この記事と結びつけて石上神宮の鉄剣を説明しようとしたのが、星野恒「七支刀考」(『史学雑誌』37、1892年)でした。‥‥百済服属の事実を示すのが、この七支刀だとされたわけです。
ただし、『日本書紀』の「七枝刀」と石上神宮の七支刀を同一とするには、難しい問題が残っていました。表面最初の年号に関して、発見者の菅は「泰始」と読み、西晋の泰始4年(西暦268年)にあてました。しかし、神功52年はそのまま西暦にすれば252年であり、製作年が贈呈年より後になってしまいます。そのうえ、神功皇后時代の記述が干支二運くりあげられていることは、紀年論争を経てすでに明らかになっていましたから、神功52年の出来事は実際には120年くりさげた西暦372年のこととなるはずで、西晋の泰始4年とは百年以上離れてしまいます。‥‥
七枝刀を『日本書紀』の記述と結びつけて百済献上説を基礎づけ、銘文の文字の解読をすすめることによって研究上の注目を集める契機となったのは、第二次大戦後の福山敏男「石上神宮七支刀」(『美術研究』158、1951年)でした。福山は年号の部分を「泰和」と読み、さらに「泰」が金石文では「太」と通用するといいます。このうえで蓋然性の高いものとして、東晋の「太和」4年(西暦369年)に比定しました。‥‥ これによって、七支刀は『日本書記』の「七支刀」といっそう強く結び付けられ、百済服属を示す確実な証拠ということになりました。
〔出典〕吉野誠『東アジア史のなかの日本と朝鮮』(明石書店-2004年)pp.40-41
『日本書紀』の干支二運繰り上げ説
近肖古以下六王の世伝につき、『(日本書)紀』に記したる年代は、韓史に異なれども、其の干支のみを比較すれば、甚能く符号せり。韓史に拠れば、近肖古は紀元1035年乙亥の歳に薨ぜしを、『紀』は、之を其の120年前に置き、其の干支は、同じく乙亥なり。‥‥唯腆支薨じて、久爾莘立たるは、韓史にては、庚申の歳なるを、『紀』は、百二十六年前の甲寅の歳に記したれば、干支も、六年の差を為せり。
両国にて別々に編述せる古代の史書に、かゝる記事の符号あるは、殆ど得難き事なり。蓋当時百済より帰化せる士人の、自ら時事を記録せる者もあるべく、又『紀註』に引きたる、『百済記』『百済新撰』『百済本記』の類、専ら彼の国の事を記したる書もありて、『紀』の撰者が、倭韓交渉の事蹟を記するに、材料乏しからざりしが故に、此の如く、精密なるなり。
さて両国の史に於て、記事も干支も、此の如く符号せるに、百二十年の差は、いかにしてか生じたる。‥‥
こは唯伝への混れにはあるまじ。『紀』の撰者が、手中の材料を整頓して、干支紀年を数字紀年に改めらるゝに当りて、偶然の誤りより、此の時代の事跡を二周甲の前に置かれたるか。然らずんば、神武紀元を遥に千三百余年の古に置かれたるが故に、神功皇后、応神天皇の御世をも、自ら其の相当の時代に置くこと能はざれば、殊さらに諸帝の在位を延ばし、遂に百済の列王をも併せて、二周甲の前に移して、其の干支のみは、百済の原書に合せ置かれたるならん。
〔出典〕那珂通世『上世年紀考』(養徳社 1948年)pp.54-56( )内は引用者〔参考〕『日本書紀』と『東国通鑑』の紀年対照表
日本書紀 東国通鑑 西暦 記事 西暦 記事 255 神功皇后55年(皇紀915年 乙亥)、百済背古王薨 375 乙亥、百済王近肖古薨 264 神功皇后64年(皇紀924年 甲申)、百済国貴須王薨 384 甲申、百済王近肖古薨 265 神功皇后65年(皇紀925年 乙酉)、百済国枕流王薨 385 乙酉、百済王枕流薨 272 応神3年(皇紀932 壬辰)百済国殺辰斯王 392 壬辰、百済王辰斯薨於狗原行宮 285 応神16年(皇紀945 乙巳)百済阿花王薨 405 乙巳、百済王阿莘薨 294 応神25年(皇紀954 甲寅)百済直支王薨 420 庚申、百済王腆支薨
歳星紀年法
歲星とは木星を指します。木星などの惑星は、それぞれの公転周期によって、星座の間を移動していきます。古代中国では、この移動区間を12の領域に分け、十二次と呼んでいました。
木星の公転周期は約12年のため、この十二次の中を毎年一次ずつ移動していきます。「歳在〜」(歳星は〜にあり」と、木星の十二次の位置によって年を表したのが、歳星紀年法です。
〔参考〕Stellarium Web
干支紀年法
木星は12年経つともとに次に戻ってしまいますから、歳星紀年法では12年間しか紀年することができません。そこで、十干と十二支を組み合わせた干支によって60年を一周期とする紀年法が考案されました。それが干支紀年法です。
ところが木星の公転周期は正確には11.862年であるため、約86年に一次ずれてしまいます。当初は木星の位置と紀年を一致させるよう「超辰」という調整方法がとられていましたが、後漢の建武26年(西暦50年)以降、こうした調整も行われなくなり、木星の運行とは関係のない60年周期の紀年法が使われるようになりました。この紀年法は、中国だけでなく、韓国や日本でも広く使われ、現在も続けられています。ちなみに今年2024年は甲辰の年になります。
| 十干 | 十二支 | 干支 | |
| 1 | 甲 | 子 | 甲子 |
| 2 | 乙 | 丑 | 乙丑 |
| 3 | 丙 | 寅 | 丙寅 |
| 4 | 丁 | 卯 | 丁卯 |
| 5 | 戊 | 辰 | 戊辰 |
| 6 | 己 | 巳 | 己巳 |
| 7 | 庚 | 午 | 庚午 |
| 8 | 辛 | 未 | 辛未 |
| 9 | 壬 | 申 | 壬申 |
| 10 | 癸 | 酉 | 癸酉 |
| 11 | 甲 | 戌 | 甲戌 |
| 12 | 乙 | 亥 | 乙亥 |
| 13 | 丙 | 子 | 丙子 |
| 14 | 丁 | 丑 | 丁丑 |
| 15 | 戊 | 寅 | 戊寅 |
| 16 | 己 | 卯 | 己卯 |
| 17 | 庚 | 辰 | 庚辰 |
| 18 | 辛 | 巳 | 辛巳 |
| 19 | 壬 | 午 | 壬午 |
| 20 | 癸 | 未 | 癸未 |
| 21 | 甲 | 申 | 甲申 |
| 22 | 乙 | 酉 | 乙酉 |
| 23 | 丙 | 戌 | 丙戌 |
| 24 | 丁 | 亥 | 丁亥 |
| 25 | 戊 | 子 | 戊子 |
| 26 | 己 | 丑 | 己丑 |
| 27 | 庚 | 寅 | 庚寅 |
| 28 | 辛 | 卯 | 辛卯 |
| 29 | 壬 | 辰 | 壬辰 |
| 30 | 癸 | 巳 | 癸巳 |
| 31 | 甲 | 午 | 甲午 |
| 32 | 乙 | 未 | 乙未 |
| 33 | 丙 | 申 | 丙申 |
| 34 | 丁 | 酉 | 丁酉 |
| 35 | 戊 | 戌 | 戊戌 |
| 36 | 己 | 亥 | 己亥 |
| 37 | 庚 | 子 | 庚子 |
| 38 | 辛 | 丑 | 辛丑 |
| 39 | 壬 | 寅 | 壬寅 |
| 40 | 癸 | 卯 | 癸卯 |
| 41 | 甲 | 辰 | 甲辰 |
| 42 | 乙 | 巳 | 乙巳 |
| 43 | 丙 | 午 | 丙午 |
| 44 | 丁 | 未 | 丁未 |
| 45 | 戊 | 申 | 戊申 |
| 46 | 己 | 酉 | 己酉 |
| 47 | 庚 | 戌 | 庚戌 |
| 48 | 辛 | 亥 | 辛亥 |
| 49 | 壬 | 子 | 壬子 |
| 50 | 癸 | 丑 | 癸丑 |
| 51 | 甲 | 寅 | 甲寅 |
| 52 | 乙 | 卯 | 乙卯 |
| 53 | 丙 | 辰 | 丙辰 |
| 54 | 丁 | 巳 | 丁巳 |
| 55 | 戊 | 午 | 戊午 |
| 56 | 己 | 未 | 己未 |
| 57 | 庚 | 申 | 庚申 |
| 58 | 辛 | 酉 | 辛酉 |
| 59 | 壬 | 戌 | 壬戌 |
| 60 | 癸 | 亥 | 癸亥 |
【参考文献】
- 那珂通世『上世年紀考』(養徳社 1948年)(→国立国会図書館デジタルコレクション)
- 岡本堅次「卑弥呼と神功皇后」(『神功皇后』)(→国立国会図書館デジタルコレクション)
【輪読図書関連年表】
| 西暦 | 国・地域 | 出来事 | ||||||
| 中国 |
朝鮮 |
日本 | ||||||
| 57 | 後漢 | 高 句 麗 |
馬韓 | 辰韓 | 弥生時代 | 倭の奴国王が後漢に朝貢し、「漢委奴国王」の金印を下賜される | ||
| 220 | 魏 | 曹丕が後漢の献帝から禅譲を受け、魏を建国 | ||||||
| 221 | 蜀 | 劉備が漢の正統を継ぐため、蜀を建国 | ||||||
| 229 | 呉 | 孫権が皇帝に即位し、呉を建国 | ||||||
| 239 | 古墳時代 | 邪馬台国の卑弥呼が魏に朝貢 | ||||||
| 240 | 邪馬台国の卑弥呼が再び魏に上表 | |||||||
| 243 | 邪馬台国の卑弥呼が三たび魏に使節を派遣 | |||||||
| 245 | 魏が邪馬台国の卑弥呼に黄幢(軍旗)を下賜 | |||||||
| 247 | 魏が帯方郡から邪馬台国に張政を派遣 | |||||||
| 263 | 魏が蜀を滅ぼす | |||||||
| 265 | 司馬炎が魏の曹奐から禅譲を受け、西晋を建国 | |||||||
| 266 | 邪馬台国の壱与が西晋に使いを送る(謎の四世紀の始まり) | |||||||
| 280 | 西晋 | 西晋が呉を滅ぼし、中国全土を統一 | ||||||
| 308 | 五 胡 十 六 国 |
西晋の懐帝が匈奴の首長劉聡に殺され、西晋が滅亡 | ||||||
| 313 | 高句麗が楽浪郡・帯方郡を滅ぼす | |||||||
| 317 | 東晋 | 司馬睿が建業(現在の南京)で晋王朝を復興(東晋) | ||||||
| 百済 | 新羅 | 4世紀初め、百済、新羅が建国 | ||||||
| 346 | 百済で近肖古王が即位 | |||||||
| 356 | 新羅で奈勿王が即位 | |||||||
| 372 | 百済が東晋に入朝し、冊封を受ける 前秦から高句麗に僧が派遣され、仏像と経文を伝える 百済の使者久氐が来朝し、服属のしるしに七支刀を献上(神功皇后52年を干支二運繰り上げ説により120年繰り下げ) |
|||||||
| 384 | 東晋から百済へ仏教が伝わる | |||||||
| 391 | 倭が高句麗を攻撃(「広開土王碑」) | |||||||
| 413 | 倭が東晋に使節を派遣(謎の四世紀終了) | |||||||
| 414 | 高句麗が好太王の事績を記念して広開土王碑を建立 | |||||||
| 420 | 宋 | 劉裕が東晋の恭帝から禅譲を受けて、南朝宋を建国 | ||||||
| 439 | 北魏 | 北魏の太武帝が華北を統一 | ||||||
| 475 | 百済が漢山城(ソウル)から熊津城(公州)へ遷都 | |||||||
| 479 | 斉 | 蕭道成が南朝宋の順帝から禅譲を受け、南朝斉を建国 | ||||||
| 500 | 新羅で智証王が即位 | |||||||
| 501 | 百済で武寧王が即位 | |||||||
| 502 | 梁 | 蕭衍が南朝斉の和帝から禅譲を受け、南朝梁を建国 | ||||||
| 514 | 新羅で法興王が即位 | |||||||
| 527 | 筑紫の国造磐井が反乱を起こす(磐井の乱) | |||||||
| 529 | 倭が近江毛野を安羅国に派遣 | |||||||
| 532 | 金官国が新羅に降伏し、併合される | |||||||
| 534 | 西魏 | 東魏 | 北魏が東魏と西魏に分かれる | |||||
| 538 | 百済が熊津城(公州)から泗泚城(扶余)へ遷都 百済の聖明王が欽明天皇に仏像や経典が送る(『上宮聖徳法王帝伝』による仏教公伝) |
|||||||
| 541 | 百済の都泗沘城で任那復興会議が開催される | |||||||
| 544 | 百済の都泗沘城で任那復興会議が開催される | |||||||
| 550 | 北斉 | 東魏の実権者高洋が北斉を建国 | ||||||
| 552 | 百済の聖明王が欽明天皇に仏像や経典が送る(『日本書紀』による仏教公伝) | |||||||
| 554 | 百済の聖王が新羅との戦いで戦死 | |||||||
| 557 | 北周 | 陳 | 西魏の実権者宇文氏が北周を建国 南朝梁の重臣陳霸先が敬帝から禅譲を受け、陳を建国 |
|||||
| 562 | 新羅が大加耶国を滅ぼし、加耶全体を併合(「任那」の滅亡) | |||||||
| 570 | 高句麗が倭に初めて使者を送る | |||||||
| 577 | 北周が北斉を滅ぼす | |||||||
| 581 | 隋 | 北周宣帝の外戚楊堅が政権を奪い、隋を建国 | ||||||
| 587 | 崇仏派の蘇我馬子らが廃仏派の物部守屋を討伐(丁未の乱) | |||||||
| 589 | 2月、隋が南朝陳を滅ぼし、中国全土を統一 | |||||||
| 592 | 飛鳥時代 | 推古天皇が即位し、明日香に都を置く | ||||||
| 595 | 高句麗から慧慈が渡来し、聖徳太子の仏教・政治・外交のブレインとなる | |||||||
| 596 | 蘇我氏が法興寺(現在の飛鳥寺)を建立(高句麗の建築様式の影響?) | |||||||
| 598 | 隋の文帝が第一回高句麗遠征 | |||||||
| 600 | 第一回遣隋使派遣(『隋書』倭国伝) 倭が新羅に出兵 |
|||||||
| 601 | 倭が高句麗・百済に使節を派遣して新羅攻撃を協議 | |||||||
| 607 | 第二回遣隋使派遣 | |||||||
| 608 | 隋が答礼使として裴世清を倭に派遣 裴世清を送るため、第三回遣隋使派遣。高向玄理、南淵請安、僧旻、倭漢福因、恵隠らを隋に留学させる |
|||||||
| 612 | 隋の煬帝が第二回高句麗遠征 | |||||||
| 613 | 隋の煬帝が第三回高句麗遠征 | |||||||
| 614 | 隋の煬帝が第四回高句麗遠征 | |||||||
| 618 | 唐 | 李淵が隋を滅ぼして唐を建国 | ||||||
| 623 | 新羅から倭に仏像が送られ広隆寺に安置される(広隆寺の弥勒菩薩像か?) | |||||||
| 630 | 倭が第一回遣唐使を派遣 | |||||||
| 632 | 第一回遣唐使犬上御田鍬を送って、高表仁が来日するが、礼を争って帰国 | |||||||
| 640 | 第二回遣隋使とともに渡海した高向玄理が、新羅を経て32年ぶりに帰国 | |||||||
| 642 | 高句麗で泉蓋蘇文がクーデターを起こす 百済の義慈王が新羅に侵攻 新羅が金春秋(のちの武烈王)を高句麗に派遣 |
|||||||
| 643 | 新羅が唐に使者を送り、救援を要請 | |||||||
| 645 | 2月、唐の太宗が第一回高句麗遠征 6月、倭で蘇我入鹿が誅殺され(乙巳の変)、高向玄理と僧旻を国博士に任ずる |
|||||||
| 646 | 倭が高向玄理を新羅に派遣 | |||||||
| 647 | 新羅が金春秋(のちの武烈王)を倭に派遣 唐が第二回高句麗遠征 |
|||||||
| 648 | 唐が第三回高句麗遠征 新羅が金春秋(のちの武烈王)を唐に派遣 |
|||||||
| 649 | 新羅が唐の衣冠礼服の制度を採用 | |||||||
| 650 | 新羅が独自の年号を廃し、唐の年号を採用 | |||||||
| 651 | 新羅の貢調使が唐風の官服で来朝、大宰府は非礼として追い返す | |||||||
| 653 | 倭が第二回遣唐使を派遣 | |||||||
| 654 | 倭が第三回遣唐使を派遣 新羅の武烈王(金春秋)即位 高向玄理没 |
|||||||
| 659 | 倭が第四回遣唐使を派遣、使節は長安に抑留される | |||||||
| 660 | 唐・新羅連合軍が百済を攻撃、義慈王が降伏し百済滅亡 | |||||||
| 661 | 新羅の武烈王(金春秋)没 倭が百済の遺臣鬼室福信らの要請により、人質となっていた余豊璋を五千の兵をつけて帰国させる |
|||||||
| 663 | 倭が百済復興を支援するため、上毛野稚子を将軍とする二万七千の軍勢を派兵(白村江の戦) | |||||||
| 664 | 倭が対馬・壱岐・筑紫に防人と烽火を置く | |||||||
| 665 | 倭が第五回遣唐使を派遣 | |||||||
| 668 | 唐・新羅連合軍の攻撃により高句麗滅亡 | |||||||
| 669 | 倭が第六回遣唐使を派遣(こののち33年にわたり遣唐使の派遣を中断) | |||||||
| 670 | 新羅が旧百済領に侵攻し、朝鮮半島で羈縻政策を進める唐と対立(羈縻政策とは、帰順した諸民族地域に羈縻州を置き、都督府の督察下での自治を認める間接統治策) | |||||||
| 672 | 倭で天智天皇の後継をめぐって内戦が起こり(壬申の乱)、勝利した大海人皇子が即位して天武天皇となり、皇后であとを継いだ持統天皇とともに唐の律令制度を導入 | |||||||
| 676 | 統一新羅 | 新羅が伎伐浦で唐軍を破り、旧百済領全域を支配し、唐の羈縻政策を排除 | ||||||
| 698 | 高句麗の遺民と靺鞨人が渤海を建国 | |||||||
| 702 | 倭が国号を日本と改め、第七回遣唐使を派遣 | |||||||
| 710 | 奈良時代 | 3月、元明天皇が藤原京から平城京へ遷都(奈良時代の始まり) | ||||||
| 720 | 『日本書紀』が成立 | |||||||
| 753 | 遣唐大使の藤原清河が唐の朝廷での朝賀の際、新羅と席次を争う(争長事件) | |||||||
| 759 | 倭が新羅遠征を計画 | |||||||
| 779 | 天皇が「表を将たざるものの境に入ら使むべからず」という詔を出し、新羅の使節を追い返す(新羅との国交断絶) | |||||||
| 784 | 11月、桓武天皇が平城京から長岡京へ遷都 | |||||||
| 794 | 平安時代 | 10月、桓武天皇が長岡京から平安京へ遷都(平安時代の始まり) | ||||||
| 828 | 新羅商人張保皐(790-841)が大宰府に来航 | |||||||
| 838 | 最後の遣唐使として、藤原常嗣や円仁らが渡唐 | |||||||
| 847 | 円仁が新羅の商船に乗って帰朝 | |||||||
| 892 | 後百済 | 甄萱が後百済を建国 | ||||||
| 901 | 弓裔が後高句麗を建国 | |||||||
| 907 | 遼 | 五代十国時代 | 唐が滅ぶ | |||||
| 918 | 後高句麗で王建が王位を奪い、高麗を建国 | |||||||
| 922 | 後百済から使節が来朝するが、通交を拒否 | |||||||
| 926 | 渤海が契丹族に滅ぼされる | |||||||
| 929 | 後百済から再び使節が来朝するが、通交を拒否 | |||||||
| 935 | 高麗が新羅を滅ぼす | |||||||
| 936 | 高麗 | 高麗が後百済を滅ぼし、朝鮮半島を統一 | ||||||
| 937 | 高麗から使節が来朝するが、通交を拒否 | |||||||
| 939 | 日本で平将門の乱が起こる 高麗から再び使節が来朝するが、通交を拒否 |
|||||||
.jpg)
-1024x742.jpg)
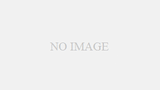
-120x68.png)
コメント