-320x180.png) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 2025-07-04(金)第12回
1.アイスブレーキング 13:10~13:40 古代史のディズニーランドともいうべき明日香村。 地図とビデオを見ながら、夏合宿について話し合いましょう。 夏合宿 第2日目プラン 明日香村観光マップ 【いよいよ飛鳥へ】古代史好き外国人が日...
-320x180.png) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 -320x180.png) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 -320x180.jpg) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 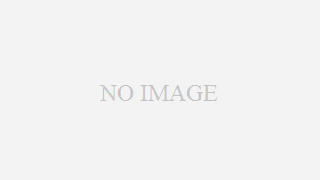 未分類
未分類 -320x180.jpg) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 -320x180.png) 2025年度授業計画
2025年度授業計画 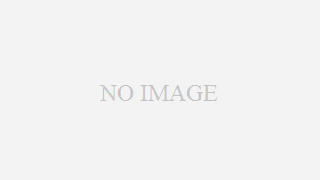 2025年度授業計画
2025年度授業計画  2025年度授業計画
2025年度授業計画 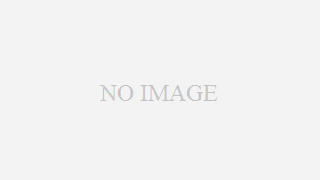 2025年度授業計画
2025年度授業計画 -320x180.jpg) 2025年度授業計画
2025年度授業計画