日中文化交流史 第3回
邪馬台国と卑弥呼の時代
魏の使節が見た古代日本
『三国志』の時代、魏の景初3(239)年のこと1。邪馬台国の卑弥呼が魏に使節を派遣し、明帝から「親魏倭王」の称号と金印、銅鏡などを下賜されました。
金印はまだ発見されていませんが、銅鏡は日本各地で見つかっています。しかし、前回の「漢委奴國王」の金印と同様、その真偽をめぐって議論が続いています。
下賜されたのは100枚のはずなのに、同じような銅鏡が300枚以上も見つかったり、「景初4年」などという実在しない年号(景初は3年で改元)が鋳込まれたものがあったりと、問題は複雑です。
しかし、日中の文化交流という視点から見た場合、こうしたモノ以上に重要なのは、このとき魏が倭に使節を派遣したことです。その目的は外交交渉というより民族誌的な調査だったらしく、正史『三国志』の中の魏志倭人伝には、この調査にもとづく倭の社会制度や風俗習慣が詳しく記録されています。
それによれば、倭の政治は中国の殷代と同じ祭政一致の神権政治で、神意は動物の骨を火で焙って占っていました。『古事記』にいう「布斗麻邇」です。卑弥呼は巫女のような存在で、その弟が政事を補佐していました。
社会の印象は総じて悪くなかったようで、「婦人は淫せず、妬忌せず」(みだらなことはせず、やきもちもやかない)、「盗窃せず、諍訟少なし」(泥棒はせず、訴訟事も少ない)と称えています。ただ酒好きは当時もいまも変わらないようで、「人性、酒を嗜む」ことが特記されています。
興味深いのは「男子は大小となく、みな黥面(顔のイレズミ)文身(体のイレズミ)す」という一節です。日本列島に顔のイレズミの習慣があったことは、縄文時代の黥面土偶や弥生時代の黥面絵画によって知られています。しかし考古学者の設楽博己氏によると、卑弥呼の時代、すなわち弥生時代末期になると、近畿地方を中心にこの習慣が消えていったことが、黥面絵画の分布状況から分かるといいます。これは黥面を刑罰の一種とする中国文化が、この地方を中心にしだいに浸透していった証でしょう。
日中の文化交流が日本列島に暮らす人びとの姿も変えていったのです。
▼顔にイレズミのある黥面土偶(縄文時代)-961x1024.png) 〔出典〕黥面土偶残欠(背面 伝長野県出土、縄文時代晩期、東京国立博物館蔵 J-36987)
〔出典〕黥面土偶残欠(背面 伝長野県出土、縄文時代晩期、東京国立博物館蔵 J-36987)
▼土器に描かれた黥面絵画(弥生時代)
.png) 〔出典〕人面文壺形土器(愛知県安城市亀塚遺跡出土、弥生時代末期、国重要文化財 安城市歴史博物館蔵)
〔出典〕人面文壺形土器(愛知県安城市亀塚遺跡出土、弥生時代末期、国重要文化財 安城市歴史博物館蔵)
注
- 『魏志倭人伝』は卑弥呼が魏に使節を派遣した年を景初2年(238年)とするが、『梁書』には「魏景初三年,公孫淵誅後, 卑彌呼 始遣使朝貢,魏以為親魏王,假金印紫綬。」とあり、『日本書紀』が引く『魏書』にも「明帝景初三年六月、倭女王、遣大夫難斗米等、詣郡、求詣天子朝獻。」とある。
.png)
-120x68.jpg)
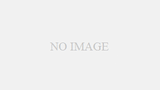
コメント