埼玉県行田市の稲荷山古墳から、1968年、1本の鉄剣が出土しました。その後の調査で剣の両面に115字の銘文があることがわかり、これが「獲加多支鹵大王」に仕えた人物のものであることが分かりました。ワカタケル大王とは雄略天皇、倭の五王の1人である倭王武とする説が有力です。
『宋書』倭国伝には、倭王武が478年に宋の順帝に送った上表文が引かれていますが、倭が内外に勢力を拡大する様子が見事な漢文で描かれています。では、この漢文、いったい誰が書いたのでしょうか?
邪馬台国と魏・晋の交流の後、日中の交流は「空白の4世紀」を迎えます。中国では311年、匈奴が晋の都洛陽を襲い、皇帝を拉致し処刑してしまいます。中原を追われた漢民族の支配層は、長江の南にある建康(現在の南京)に都を移し、以後270余年にわたり江南に逼塞することになります。
中国が朝鮮半島支配の拠点とした楽浪郡は高句麗に併合され、帯方郡も土着の韓族・濊族に滅ぼされてしまいます。その結果、倭と中国をつなぐ交流のルートが断たれてしまったのです。
その後、朝鮮半島から漢の皇裔と称する人びとが日本列島に渡って来ました。漢氏と呼ばれる渡来人です。日本古代史の研究で知られる上田正昭氏は、これは中華にこじつけた言い伝えで、朝鮮半島南部から渡来した氏族だといいます。
しかし、彼らの中から東文氏や西文氏といった漢字を扱う専門集団が誕生したところをみると、関西大学の西本昌弘氏が説くように、楽浪郡や帯方郡の滅亡後、百済などを経て渡来した中国系の遺民と考えるのが自然でしょう。
銘文のある刀剣は、熊本県玉名郡の江田船山古墳からも出土しています。鉄刀の峰に75字の銘文があるのですが、王の名は一部が欠けていて読めませんでした。しかし稲荷山古墳の鉄剣の発見により、この王の名も「獲■■■鹵大王」であることが分かりました。
面白いことに、この鉄刀には銘文の筆者の名も刻まれていました。「書者は張安なり」。恐らく朝鮮半島から渡来した中国系遺民の1人だったのでしょう。
この張安のような人びとが、当時の国際語であった漢文を使い、倭の国づくりを支えていたのです。
| 江田船山古墳出鉄刀銘文(熊本県) | 稲荷山古墳出土鉄剣銘文(埼玉県) |
.png) |
.png) |
-scaled.jpeg)
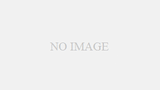
-120x68.jpg)
コメント